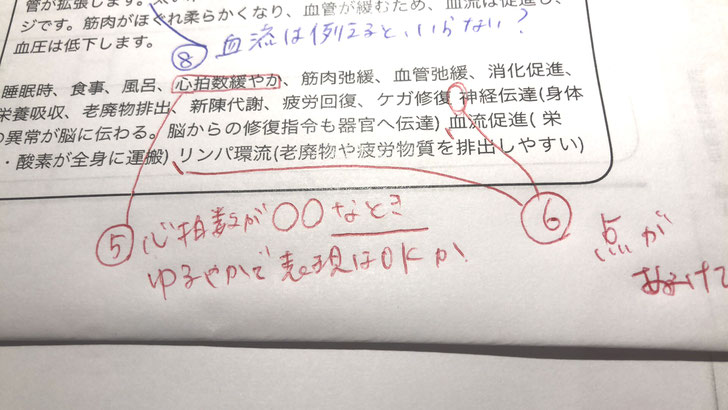
経歴にさえならないが、専門学校に通っていた(中退でなく除籍扱いらしい。学校の名前は仰々しいので、伏せさせてもらうが、編集・校正・物書きのスペシャリストになる為の学校だ)。
校正というものの鉄則は、感情を入れずに文字を追うことになる。そこに感情が入り込む事で、当たり前の思い込みが生じ、誤字脱字の見落としが起こりうるからだ。
それは苦痛な時間、面白みに欠ける時間であった。結果、自然と遅刻・早退・欠席の連続になり、よく嫌味や説教をされたものだ。僕の態度からは、やる気あるの?と問われても仕方ないものであった。
しかし、それには訳がある。もっと言うなら、言い訳がある。
「あなた達が、仮にどんなに優れていても、就職時、大学卒業の冠を持った経歴には全く敵わないのだから、せめて地味な作業である校正くらい、きちんと習得しなさい」
初回の授業で言われた言葉。
それは事あるごとに、形を変え似たような言葉として浴びせられていた。そんな言葉を聞くたびに、負け犬の烙印を押されているようで、不愉快を通り越し侮辱として心が軋むばかりだった。
校正という仕事もどこか馬鹿にされ、とどめに人間を否定されているようにしか感じられなかった。
今、振り返れば、現場感としてそれは正しいのであろう事も、大卒に勝てる要素がないという理屈も理解出来るのだが、ただただ蒼く、幼さという武器しかなかった僕には反発する事が精一杯だったのだ。
「校正」という場で、見返してやりたいという気持ちは全くなく、ただただ、足が遠のいていった。僕にとって、その時間は、期待値ゼロの人間は伸び代がないという名のゴーレム効果の典型であったのだ。
だからこそ、その後に遭遇するプロの校正マンに出会うとドキドキするのだ、成し得なかった事を叶えた人間として、すげえなぁ、この人、感情を入れずに文字を追いかける事が出来るんだ。
若かりし頃に染み付いた苦手意識は、今では校正マンへの尊敬になっているのだ。







